【特別インタビュー】家族を看る子どもたち ヤングケアラーという現実[2022年11月号掲載]
※本記事は、2022年11月に発行されたあいらいふ vol.162に掲載されたものです。
情報は記事執筆当時のものであり、2025年3月時点の状況とは異なる可能性がございます。
近年、「ヤングケアラー」という言葉が大きな注目を集めています。その定義は国や支援を行う団体によって異なりますが、一般的に昼間は学校に通い、帰宅してから病気や障がいを抱える家族のケア、家事などを日常的に担っている子どもたちのことを意味します。
彼らをとりまく生活環境と社会的な課題、今後必要とされる支援のあり方について、自身もヤングケアラーとして育ち、現在はケアラーたちのサポートや啓発活動を展開する「一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会」(以下、CAN)の代表理事を務める持田恭子さんにお話をうかがいました。

日本の「家族主義」を改善したい
その思いの背景にあるものは?
持田代表理事
厚生労働省のHP「ヤングケアラーについて」には、子どもたちが行っているケア行為の一部を事例化したイラストが掲載されていますが、そこには「法令上の定義はない」と明記されています。
ここでヤングケアラーを定義づけてしまうと、掲載された例以外がヤングケアラーの定義から外され、「自分は大したことをしていないから、ケアラーではない」とか、「目に見える形での介護(重たい介護)をしていないから、ケアラーだと名乗ってはいけない」と、子どもたちが思い込んでしまうおそれがあるからです。
私たちCANも、“こういった子どもがケアラーです”と、レッテルを貼るような捉え方をすることは極力避けています。「さまざまな事情で家族のケアをしている子どもや若者」といった、もう少し幅広い視点で彼らと向き合い、子どもたちが自分自身でヤングケアラーかどうかを判断できるよう、ワークショップやオンラインによる交流の場を設けています。
CANでは、日頃の活動の一環として、ケアをする中高生を対象とした「探求プログラム」と、「ほっと一息タイム」を毎月1回、オンラインで開催しています。
「探求プログラム」では、家族のケアをしているきょうだい児(難病や障がいなど、日常生活で手助けや介助が必要な兄弟姉妹がいる人)やケアラーが集まって、ケアとは何かを学んだり、自分を大切にすることについて一緒に考えながら、自分自身の気持ちと向き合い、将来の夢などを語り合っています。
一方、「ほっと一息タイム」は、テーマを設けない気軽な集まりです。学校での出来事や推し活(自身にとってイチオシの人物やキャラクターである“推し”を応援する活動)の話をして、みんなで楽しい時間を過ごしています。
家族をケアしている子どもにとって、ケアは日常生活の一部ですから、周りの人たちから「かわいそう」と思われたくない。また、家庭で起きている出来事や自分の気持ちを先生や同級生に話そうとしても、ケア経験がなければきっとわかってもらえないだろうと相手に気を使ってしまい、なかなか打ち明けることは難しい。
でも、ケアラー同士のこうしたオンラインの集まりであれば、気兼ねなく話せるので、家族をケアする環境の中でも、子どもたちは解放感を得られるようです。
日本には「身内が家族の世話をするのが当たり前」という、「家族主義」の考え方が根強く、ケアや介護を身内だけで抱え込んでしまう傾向があります。私たちは、こうした風潮が改善され、「家族だけでケアを抱えなくてもいい」社会が実現することを目指して活動しています。
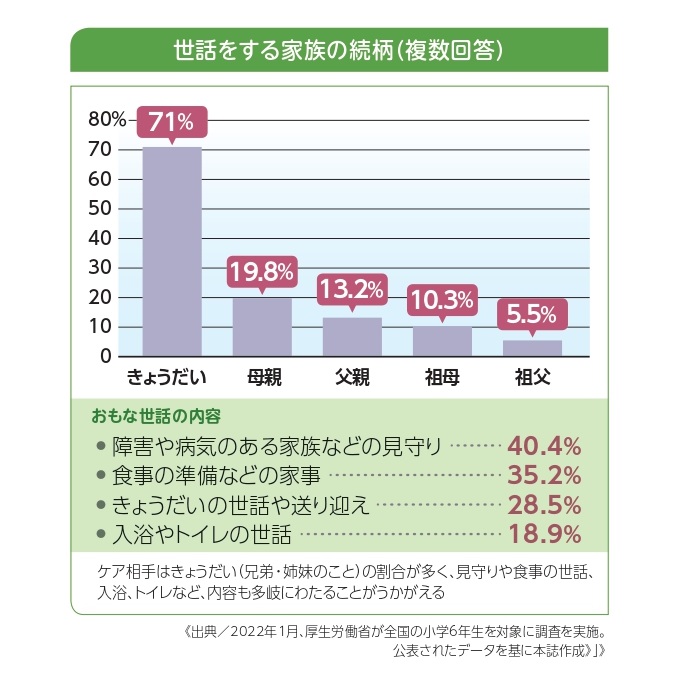
問題解決だけではなく
こどもたちのニーズを知ってほしい
2022年度から、厚生労働省ではヤングケアラーの支援体制強化事業を推し進めています。相談支援事業などを含め、福祉や介護の課題解決に向けた支援対策の議論も始まりました。
公的支援の介入を必要としている方々もいるので、課題解決型の支援ももちろん大切なのですが、家族のケアをしている子どもたちが「何を望んでいるのか」を理解して、把握することも必要です。
ケアラーは介護者ではないので、今までの支援者に向けた対策ではなく、新たな視点で家族を支えることを考えていかなければなりません。ケアをしている子どもは、どのような暮らしをしていて、どのようなことを考え、何を必要としているのか。
そうしたことを大人が理解していくことで、ようやく子どもたちとのコミュニケーションが始まります。
現在、行政機関では、ヤングケアラーの相談支援体制の整備が進んでいますが、子どもたちは「直接、行政の窓口に相談するのはハードルが高い」と言っています。当初は、ケアラーかもしれない子どもを支援するために、どの窓口につなげればいいのかを知りたい支援職や、一般の方からの相談に対応していくのではないでしょうか。
そのためにも、地域の民間支援団体と行政との間で連携が強まっていくことを期待しています。
CANが提供する「探究プログラム」に参加した子どもたちは、「同じ境遇の仲間ができて、安心感を得られた」と言っています。大人はあまりアドバイスをせず、子どもたちが自由に話したり考えたりできる環境づくりを心がけています。
プログラムに参加するうちに、子どもたちは他者の意見を参考にして自分なりの対応策を考えるようになり、周囲に相談しながら成長していきます。
例えば、「自分の感情と向き合うこと」をテーマとしていたときは、家族のケアだけでなく、日常の些細な出来事についてみんなで話し合うことで、イライラの感情が解消され、大人たちの手を借りることなく、ポジティブな考え方に向かっていくことができました。
さまざまな局面で、他人に相談しづらく、自ら判断するしかない環境で育っている子どもたちは、大人からアドバイスされるのではなく、自分自身の力で物事に対する気付きを得て、変化していくことにより、大きな自信を持てるようになります。
同プログラムでは、こうした子どもたちと似た境遇で育ち、さまざまなケア経験を持つ大学生のピアメンター(助言者)が、ボランティアとして話し相手になっています。ケアラー同士だからこそ、より深く共感し合えるのではないでしょうか。
ケア体験が子どもの発育や
将来に与える影響とは…
ケアラーは、家族からの頼まれごとをほぼ100%受け入れて、世話や介護をするという生活を幼い頃から続けています。
家族からの依頼を拒否すれば、生死に関わるかもしれないし、状況がひどくなってしまうかもしれないので、断る選択肢を持ちにくく、他者に頼る発想も浮かばず、自分一人で引き受けて、頑張ってやり切ろうとするのです。
高校生になると、将来の進路を考える時期になりますが、自分の夢や本当にやりたいことを横に置いて、家族のことを優先する子どもたちもいます。
日常的に頑張り過ぎる習慣が身についてしまうと、心や身体が疲弊していることに気づきにくい状態に陥ることも少なくないのです。
大人になってから、原因不明の体調不良に悩まされることもあるため、若いうちからメンタルをケアしながら健全な心身を整えておくことは大切です。ヤングケアラーへの支援は物理的なものと精神的なもの、両輪でのサポートが必要であると理解していただけるとうれしいです。

ケアをする子どもたちとともに
私たち大人ができること
私たちは2021年の12月に、きょうだい児を主役にした短編映画『陽菜(ひな)のせかい』を制作しました。
自閉症で知的障害を伴う兄がいる17歳の高校生、陽菜。彼女の揺れ動く心の葛藤を描き、両親、友人、学校の先生など、主人公を取り巻くさまざまな人たちの視点で物語は進みます。映画をご覧になった方々が、それぞれの立場で何かを感じ、考えるきっかけになればうれしいですね。
この作品は、私の高校生時代の体験をベースにしたものです。制作の過程では、現役の高校生のきょうだい児にもインタビューを行ったのですが、当時、自分自身がきょうだい児として抱えていた心の葛藤が、世代を超えても変化していないことに驚きました。
この40年間で、障害者や高齢者を対象とした法律は改正され、福祉・介護サービスは拡充されました。一方で、私が高校生だったころから現在まで、ケアラーへの配慮はなされてこなかったということです。
ヤングケアラーという存在がようやく認識され、国が動き、行政が手助けをする気運が高まってきた「今」だからこそ、一人ひとりの意識が変わっていけるように、私たちはアクションを起こさなければなりません。
私たちは、ケアをしている子どもたちが、家族を守っていることを誇りに思いながら、同時に夢を持つことができ、自分の人生を切り拓いていける、そういったことが可能な社会を作っていきたいと考えています。 もし、読者の方が家族のケアをしている子どもに出会ったら「自分だったらどう思うのかな」と、共感的な理解を持って接していただきたいと思います。そうした思いを少しでも持っていただければ、未来はきっと変わり、寛容な社会になっていくはずです。
【プロフィール】
一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会 代表理事
持田恭子さん
外資系企業で管理職や専門職に従事した後、2013年にケアラーアクションネットワーク協会を設立し、2019年の法人化を経て代表理事に就任する。自身が小学生の頃から、母親の心のケアやダウン症候群がある兄の生活面のサポートを行ってきた。後年、要介護5になった母親の在宅介護と兄の世話、仕事を両立させながら、似たような立場の人との交流を目指して「きょうだい会」を始める。現在も、きょうだい児やケアラーを対象にした交流会やワークショップなどのプログラムを通じて、「家族だけでケアを抱えなくてもいい」社会づくりを目指す。
===取材協力===
一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会
https://canjpn.jimdofree.com
取材・文/神﨑恭子
撮影/居木陽子
豊かなシニアライフのための情報誌『あいらいふ』編集部
【誌名】『あいらいふ vol.162(2022年11月発行号)』
【概要】初めて老人ホームを探すご家族の施設選びのポイントをさまざまな切り口でわかりやすく解説。著名人に介護経験を語っていただくインタビュー記事のほか、人生やシニアライフを豊かにするためのさまざまな情報や話題を取り上げて掲載。
【発行部数】4万部
【配布場所】市区役所の高齢者介護担当窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・病院・薬局など1万か所












