【ソーシャルワークの現場から-支援連携の輪-】[京都]支援センター・ひなたぼっこ / 介護支援専門員(ケアマネジャー)・北川 裕之 氏

介護支援専門員(ケアマネジャー)・北川 裕之氏
care manager/Hiroyuki Kitagawa
自分を必要としてくれる誰かがいる
脳梗塞を患って孤立を深めていた祖父が、孫である北川さんが訪れると表情をほころばせ、一緒に外出することにも前向きさを見せてくれた。そのときに感じた「人が再び元気になる瞬間に立ち会う」喜びが、福祉職を志した原点となった。ケアマネジャー(以下、ケアマネ)として、利用者に寄り添ったサービスを提供する介護支援専門員、北川裕之(きたがわ ひろゆき)さんに、介護へのお話しをうかがった。
「将来は家業を継いでほしい」期待されて育った幼少期
■あいらいふ編集部(以下、あいらいふ):
本日はお時間をいただき、ありがとうございます。最初に、北川さんのご出身や生い立ちについてお聞かせください。
■ケアマネジャー・北川さん(以下、CM北川):
兵庫県尼崎市で生まれ、大学4年生までを尼崎で過ごしました。小学生の頃は、学年を問わず近所の子どもたちと集団で登校するような、昔ながらの温かい環境の中で育ちました。
父は祖父から継いだ鉄工所を経営しており、ゆくゆくは工業大学に進むように勧められました。長男ということもあり、後継者として期待されていたのです。でも、幼い頃から工場の鉄の匂いが苦手で、家業を継ぐことには抵抗がありました。
私の家は習い事に熱心な家庭で、学校が終わるとすぐに家に戻り、そのまま塾へ通う日常を送っていました。ピアノを習っていた時期もあったものの、何とも不器用で、思うように演奏できなかったことが印象に残っています。
脳梗塞で倒れた祖父との思い出が福祉職を志す原点に
■あいらいふ:
介護の仕事を選んだきっかけは何だったのですか?
■CM北川:
子どもの頃は、夏休みや冬休みに、祖父や祖母の家に行くと、いとこもいたりして、すごく楽しかったんですよ。そこが自分にとっての癒しの場所でした。
そんなある日、祖父が脳梗塞を患い、その影響で身体が不自由になってしまいました。退院後も、家に閉じこもりがちでした。でも、私が遊びに行くと、顔を明るくしてくれて、喜んで一緒に散歩したり、嬉しそうに昔話や楽しい話を聞かせてくれていました。
そのときに、自分も福祉とか、ボランティアとか、誰かに喜んでもらえる仕事がしたいという気持ちが芽生えたのです。
この体験こそが、今の介護の仕事をするようになった大きなきっかけでした。
■あいらいふ:
家業を継ぐという道は選ばなかったのですか?
■CM北川:
はい。鉄工所は父の兄の息子が継ぐことになりました。
最初は父も、私が介護の道へ進むことに強く反対しました。「自分自身の世話さえ満足にできないのに、人のことなんかできへんぞ」と説教されましたね。
ですが、私自身、給料の良い仕事に就きたいとか、出世したいとか、もともとそういう欲がありませんでした。
ただ、福祉関係の仕事がしたいという自分の熱意に押され、最後には父もあきらめて、私が社会福祉専攻のある大学の進学を認めてくれました。
当時、社会福祉学を専攻できる大学はまだ少なかったため、京都の龍谷大学に進学。そして、大学卒業後は滋賀県に所在する特別養護老人ホーム(特養)へ就職しました。
■あいらいふ:
特養では、どのようなお仕事をされていたのですか?
■CM北川:
生活指導員という役職で働き始めました。ご入居者の生活記録の管理や、入所・入院時の手続き、そして役所とのやり取りが主な業務内容です。しかし、実際に仕事をする中で、思い描いていた理想との違いを感じるようになりました。
その施設では、認知症の方が落ち着かなくなって外に出ようとすると、シャッターを閉めて外出させないように対応していました。
私は「認知症の方の行動には必ず意味がある」と考えていたので、その方の気持ちを理解しようと、一緒に外を散歩したり、話を聞いたりしていました。
ところが、施設に戻ると、上司から「何をしとるんや!!」と叱責されることが度々あったんです。
施設はいわゆる家族経営で、本来の業務以外に鶏小屋の掃除や親族宅の雑用といった仕事まで任される状況(笑)。何より納得がいかなかったのは、ご入居者との向き合い方でした。
正直、「ここにいても自分の目指す介護が実現できない」と感じ、勤務開始から9か月で退職することを決めました。
「もっと介護について学びたい」と悩み続けた末、龍谷大学の大学院に進学する決意を固めたのです。
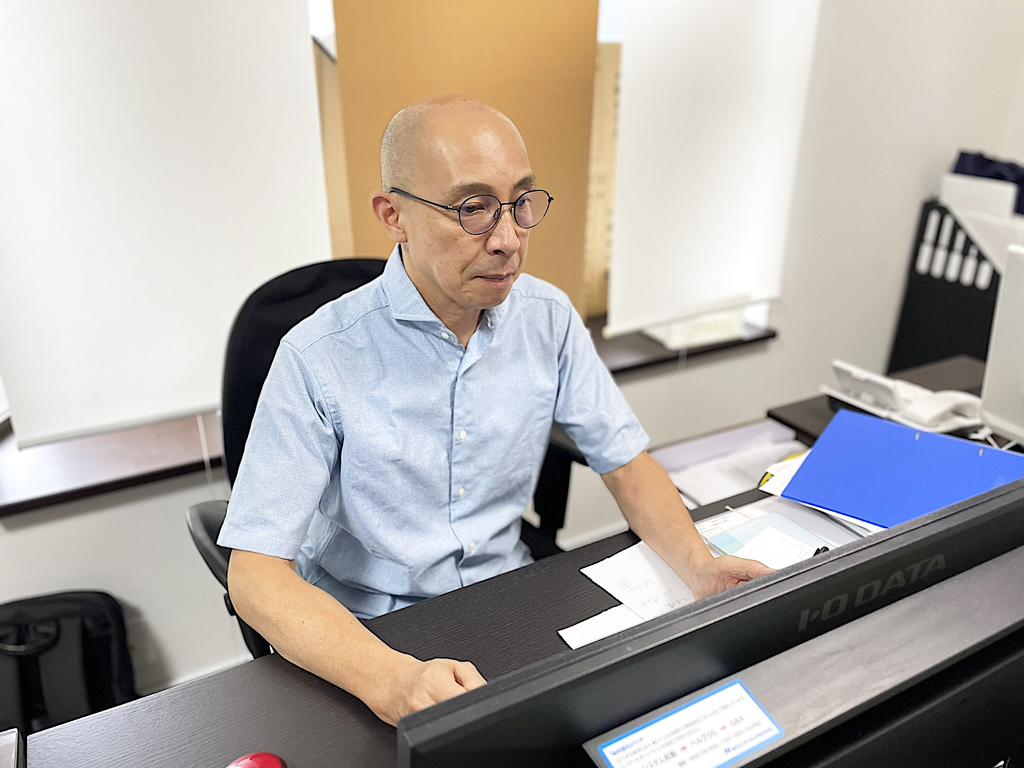
大学院で学んだ暮らしをとらえる視点「調査活動」で知った介護の現実
■あいらいふ:
大学院ではどのようなことを学んだのですか?
■CM北川:
大学院では、調査活動に熱心に取り組みました。とくに印象的だったのは、夏休みに実際に地域のお年寄りの家を訪問して、生活の実態を調査する機会があったことです。
調査票を片手に、初めて会う方に話を聞くのは難しく、うまくいかないことも多々ありましたが、それ自体が有意義な勉強の機会になりました。そして、チームで何軒も回っていくうちに、介護の問題は単に家族内の問題ではなく、経済的な状況や孤立といった、さまざまな社会背景とつながっていることを痛感しました。
あるお宅では、ゴミが散乱し、生活が困窮している現実がありました。暮らしが苦しい家庭ほど、なかなか他者に相談できず、社会的にも取り残されてしまうという現実に直面し、衝撃を受けたのです。
この調査活動を通して、介護の現場だけでなく、社会全体の構造にも目を向けるきっかけをもらいました。それまで知らなかった「制度だけでは救えない生の声」と対峙し、社会のひずみのようなものを肌で感じることができました。とても貴重な経験でしたね。
■あいらいふ:
調査活動の中で、記憶に残っている事例はありますか?
■CM北川:
一人暮らしをしている40〜50代くらいの女性のお宅にうかがったことがありました。その方の話を聞いて、胸がしめ付けられるような気持ちになったのです。なんとか力になりたいと思っても、何もできない自分がいて。そのとき、なんというか、その方を「愛おしい」と感じたんです。
調査結果をチームで共有するときに、その感情を正直に伝えると、先輩に「そういう言葉を軽々しく使うもんじゃない」と諭されました。今考えると、それは「その人の置かれた厳しい状況を、安易に理解したつもりになるな」という戒めだったに違いありません。その人の本当の気持ちは、そう簡単にはわからない、ということを教えてくれたのです。
この経験から、仕事との向き合い方を深く考えるようになりました。ケアマネとして、すべての人に公平・公正に対応することはもちろん大事です。でも、私自身、どうしても感情移入してしまうし、心のどこかに「この人のために、もっと何かしてあげられるんじゃないか」という気持ちが残るんです。
この思いが、すべての人に受け入れられるわけではない。でも、受け入れてくれた人のためには全力で応えたい。自分はそういう人間なんだなと、あらためて気づきました。
■あいらいふ:
大学院修了後は、どのような経緯でケアマネを目指されたのですか?
■CM北川:
大学院を3年かけて卒業した後、地域住民の運動で設立された特別養護老人ホームに就職しました。当時、この施設が研修会で発表した高齢者に寄り添ったケアの実践報告に感銘を受け、「ここで働きたい」と思ったことがきっかけでした。
ちょうど事業を拡大しているところで、特養の相談員から始まり、デイサービスやショートステイの相談員、さらには居宅ケアマネなど、さまざまな業務をここで経験しました。同法人が運営しているさまざまな事業所で介護福祉に関する実践を学ぶことができました。
その後、現在の居宅介護支援事業所「ひなたぼっこ」のケアマネとして携わっています。
刑期を終えた男性との出会い「献体」に込められた願い
■あいらいふ:
ケアマネとしての豊富なご経験の中で、とくに忘れられないエピソードはありますか?
■CM北川:
私のキャリアの中で印象に残っているのは、刑期を終えて自宅に戻られた方のケースです。刑務所で脳出血を起こし、その後遺症でマヒがあり、生活保護を受けながら一人暮らしをされていました。
幻覚や妄想から近隣トラブルを繰り返す大変な方で、前任のケアマネから「担当してくれないか」と引き継ぎを受けたのです。とにかく頑固で、トイレに行くために何度転倒を繰り返しても、諦めない。怒鳴られることも多かったのですが、その方の「自分で何とかしたい」という強い気持ちを理解したいと思い、一生懸命関わりました。
あるとき、彼が私に「自分が死んだら献体したい」と打ち明けてくれました。若い頃にひどいことをしてきたから、せめて世の中のために貢献したい、という思いからでした。でも、献体には親族の同意が必要です。ご本人は群馬出身で、長年疎遠になっていた弟さんがいらっしゃいました。
弟さんは、最初は関わりたくないと言っていました。しかし、弟さんの娘さん、つまり姪御さんが「小さい頃、おじさんによくしてもらった。協力します」と手を差し伸べてくれたのです。最終的に、さまざまな関係者の協力のおかげで、献体の手続きが実現しました。
この経験を通じて、私自身、たくさんのことを学びました。彼のようないわゆる困難事例と呼ばれるケースでも、「この人の力になりたい」と、協力してくれる医師や看護師、関係事業所が世の中にはあるということを知ったのです。
多くの人が親身になって彼と関わる中で、ご本人も徐々に心を開き、最後には「気をつけて帰りや」と優しく私に声をかけるなど、温かい一面を見せてくれるようになりました。人と人とのネットワークを築き、その方の願いを叶えられたことは、ケアマネとしての、私の誇りになりました。
“教科書通り”でなくその人の人生を支えたい
■あいらいふ:
ケアマネという仕事を通して楽しかった思い出を教えてください。
■CM北川:
以前の職場での出来事ですが、施設の家族会の役員をされていた男性を担当したことがありました。ある時から、彼が認知症の症状を見せ始めたと言われるようになり、同じ役員の方から「ようすを見に行ってほしい」と頼まれたんです。
実際に会いに行くと、コミュニケーションがうまく取れなくなっていて、症状が進んでいることが分かりました。車の運転もままならず、これまでのように自由に出かけられなくなり、孤立し始めていました。
そこで、事務所で簡単な作業を手伝ってもらうことにしました。最初は「やることがない」とすぐに帰ってしまわれましたが、そのうち毎日通ってくれるようになったのです。ただ、デイサービスという集団生活にはなかなか馴染めないようすでした。
そんなときは、ラーメン屋に誘って一緒にご飯を食べながら話をしたり、お風呂に入りたがらない日には、ヘルパーさんと私と3人で銭湯に行ったりもしました。今で言う「シャドウワーク」かもしれませんが、やっぱりお風呂に入れると笑顔になるんですよ。ご本人が喜んでくれるなら、それは必要な手助けなのではないかと、私は考えています。
今にして思えば、ずいぶん型破りなケアをしていたと思いますが、当時勤めていた施設では、介護保険が始まる前から、必要なことは何でもやろうという自由な風土がありました。
私はそこで長く働かせてもらったので、まわりも「北川なら、仕方ないな」と、ある程度は受け入れていてくれたのかもしれません。おかげでやりたいようにさせてもらえて、楽しかった記憶として心に残っています。
■あいらいふ:
北川さんがケアマネとして大切にしていることは何ですか?
■CM北川:
介護保険サービスには、できることとできないことがあります。でも、人の暮らしや人生を考えたとき、そこに線引きなどはありません。たとえ社会保障の枠を超えても、「その人の人生をしっかりと支えたい」という思いを大切にしてきました。
もちろん、何でも自由にできるわけではありません。教科書通りに決められたことをやるのが良い仕事だという考え方もあるけれど、私自身はきっと、そこに収まらない人間なんだと思うのです。
あるとき、上司から「うちの法人には、君のような人間も必要だ」と言われたことがあります。この言葉が私の励みになりました。
■あいらいふ:
この仕事は、北川さんにとって天職なのではないですか?
■CM北川:
そう言っていただけるのはありがたいのですが、実際、「しんどい、辞めたい」と思いながら続けてきた部分もあります。
でも、現場でご利用者と関わっていると、簡単には辞められない。「やらなあかん」という強い気持ちになります。ご利用者に必要とされている間は、働き続けようと思います。
実は今、ケアマネ会の活動の一環で、介護のマニュアルを作る新人育成チームに入っていまして、まだまだやらなければならないことがたくさんあります。
自分らしくいられる場所で人とのつながりを育む
■あいらいふ:
北川さんにとって、この仕事のやりがいと、介護支援を通して伝えたいことは何ですか?
■CM北川:
介護の仕事のやりがいは人それぞれだと思いますが、私にとっては、「自分のやりたいように仕事ができること」です。
「ケアマネの仕事は大変」というイメージをもたれがちですが、私は自分のやり方を通して「ケアマネって、こんなこともできるんだ」という可能性を、のちに続く人たちに伝えたいと思っています。
介護保険の枠にとらわれず、その人の人生を丸ごと支えるために何ができるかを考え、行動する。私のやり方は、少し変わっているかもしれませんが、ご利用者に深く寄り添い、信頼関係を築けたときに、心から「この仕事をしていてよかった」と感じます。
私にとって「ひなたぼっこ」は、自分らしくいられる大切な場所です。これからも、自分らしさを大切にしながら、新しい出会いや人とのつながりを育んでいきたいと思っています。
【プロフィール】
居宅介護支援事業所
支援センターひなたぼっこ
介護支援相談員
北川 裕之
兵庫県尼崎市生まれ。龍谷大学にて社会福祉学を学び、卒業後、特別養護老人ホームに就職。その後、同大学院にて福祉の学びを深める。ケアマネジャーとして数多くの支援経験を積み重ね、介護支援相談員として、利用者に寄り添った介護サービスの提供に努める。
===取材協力===
居宅介護支援事業所
支援センター ひなたぼっこ
京都府京都市北区紫竹西南町67-20
取材・撮影:鈴木孝英/文:山田ふみ
豊かなシニアライフのための情報誌『あいらいふ』編集部
【誌名】『あいらいふ vol.179(2025年9月25日発行号)
【概要】初めて老人ホームを探すご家族さまの施設選びのポイントをさまざまな切り口でわかりやすく解説。著名人に介護経験を語っていただくインタビュー記事のほか、人生やシニアライフを豊かにするためのさまざまな情報や話題を取り上げて掲載。
【発行部数】4万部
【配布場所】市区役所の高齢者介護担当窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・病院・薬局など1万か所












