【ソーシャルワークの現場から-支援連携の輪-】[京都]まごのて北山 / 介護支援専門員(ケアマネジャー)・津﨑 朋美 氏

介護支援専門員(ケアマネジャー)・津﨑朋美氏
care manager / Tsusaki Tomomi
その人らしい「生き方」を
チームワークで支援する
介護を必要とする方やご家族の相談に乗り、適切な介護サービスが受けられるようにサポートすることが、ケアマネジャー(以下、ケアマネ)の大切な仕事。高校生の頃に経験した祖母の在宅介護が、この道に進むきっかけになったという津﨑さんに、介護への想いをうかがった。
がんを患った祖母の介護が
ケアマネを目指す原点に
■あいらいふ編集部(以下、あいらいふ):
本日はお時間をいただき、ありがとうございます。最初に、ケアマネというご職業を選んだ経緯について、お聞かせいただけますか?
■ケアマネ・津﨑さん(以下、CM津﨑):
高校生のときに、祖母ががんを患い、家族全員で介護にあたることになりました。病院では検査した時点ですでに手遅れとされ、余命わずか数か月と宣告を受けました。そのとき、私たちには介護に関する知識がまったくなく、どの選択が正しいのか手探りの毎日だったんです。出来る限り状況に対応するために必死でしたね。兄を含む6人きょうだいの長女だった私は、慣れない介護の日々の中で、兄と2人で祖母を抱えトイレに運ぶ際、誤って落としてしまうという失敗も経験しました。
その状況で、もし介護に詳しい知識を持った人が近くに一人でもいてくれたら、どれだけ心強かっただろう…と感じたのが、この道を意識し始めたきっかけです。
■あいらいふ:
ご親族の介護の経験が、進路を決めるきっかけになったのですね。
■CM津﨑:
まさに進路に悩んでいた時期と重なっていて、私が介護をしている姿を見ていた祖母の友人から、「介護の仕事に向いているんじゃない?」と言われたことが、大きな後押しとなりました。そして高校を卒業後、『京都YMCA国際福祉専門学校』に進学し、介護福祉士の資格取得を目指すことにしました。
「在宅復帰」をサポートする
老健の現場へ
■あいらいふ:
学校を卒業後、最初の就職先はどのような場所だったのでしょう?
■CM津﨑:
最初に勤めたのは、京都市内にある老人保健施設(老健)でした。老健は、リハビリを経て在宅復帰を目指すご利用者が多いので、高齢者の自立を支援するという仕事内容に魅力を感じました。施設自体も明るい雰囲気で、ここで働いてみたいと思ったんです。
■あいらいふ:
京都を離れようという選択肢はなかったわけですね。
■CM津﨑:
仕事の都合などで滋賀や大阪に引っ越される方もいらっしゃいますが、私の場合は両親がこちらにいますし、何より京都が好きなんです。それに、夫も京都の出身で、今は3人の子どもと一緒に暮らしています。本当に子育てには良い環境だと思いますね。たくさんの神社仏閣があって、人々も温かいです。ここにいるだけで心が安らぎます(笑)。
■あいらいふ:
老健での勤務は、いかがでしたか?
■CM津﨑:
はじめての経験でしたが、本当に楽しい時間でした。職員の方々が、全員で目標に向かって協力し合う体制が整っていましたし、リスク管理についても、スタッフ間でしっかりと話し合いながら、対策を行っていました。また、リハビリや日常ケアを通じてご利用者の生活を支えるためには、チームワークが欠かせないことを改めて実感しました。介護職員だけでなく、看護師やリハビリスタッフなど、多職種が連携することで初めて、業務はスムーズに成り立つんだと感じました。そのため、10〜15人くらいのチームで密に話し合い、常に一丸となって動いていましたね。
大変なこともありましたが、たまに「へましちゃった!」ということがあっても、みんながフォローし合える働きやすい職場環境でした。結果的に、老健で10年間現場の経験を積むことができました。
■あいらいふ:
老健で、とくに思い出深かったエピソードを聞かせてください。
■CM津﨑:
認知症を患っていて、ご自身がどういう経緯で施設に入所されたのかをまったく把握されていない方がいらっしゃいました。夜中にトイレへお連れした際、突然髪をぐっとつかまれて放してもらえず、看護師さんの力も借りて、なんとか落ち着いてもらったんですが、正直、ショックな体験でしたね。
別のご入所者のエピソードでは、朝のケアをすべて終え「準備万端だな」と思った直後に、「もうやめてくれ!」と叫ばれ、リハビリパンツを勢いよく破かれてしまったこともあります。本当にいろいろなことを経験が今の私の公私すべてに活きています。
■あいらいふ:
その後のキャリア形成について教えてください。
■CM津﨑:
介護現場で経験を積む中で、もっと広い視野で支援に取り組みたいと思うようになりました。そして、最初の子どもが生まれたタイミングで、新たな可能性を求めてケアマネの資格を取得しました。 その後は、老健施設から地域包括支援センターへと職場を移し、ケアマネとして勤務。現在は居宅介護支援事業所(以下居宅)でケアプランの作成に取り組んでいます。
最期を迎えるその時まで
ご利用者の支援に力を尽くす
■あいらいふ:
地域包括支援センターでの仕事と居宅としての仕事に、どのような違いを感じましたか?
■CM津﨑:
地域包括支援センターでの業務は、ご利用者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、さまざまなサービスを調整する必要があり、幅広い知識に加えて、とりわけ関係機関との連携が重要視される仕事でした。幅広い知識だけでなく、関係機関との連携がとても重要でした。居宅とは少し性質が異なり、地域のいろいろなサービスを、利用者の状況に合わせてつなげることが重要だと感じました。
居宅のケアマネになって感じたのは、在宅介護の難しさです。とくに、ご高齢者同士で介護し合う「老老介護」の場合、介護者の方が体力面でも精神面でも限界を迎えていることが多くあります。その中で、ご本人とご家族の希望を尊重し、介護士さん、保健師さん、医師と協力しながら、望む介護プランを作成できるかがポイントになります。
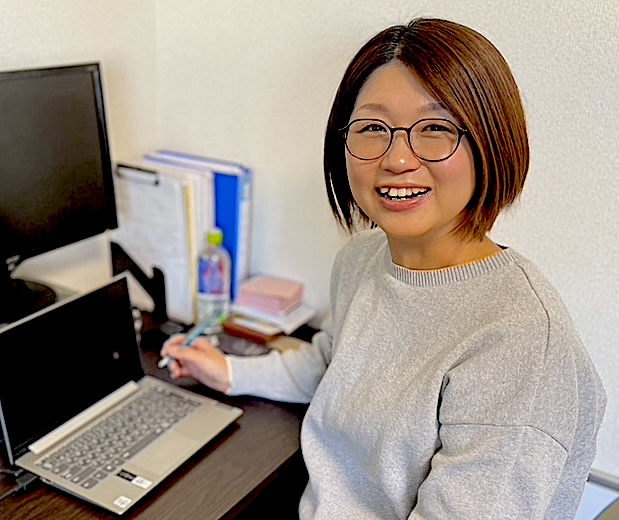
■あいらいふ:
ご利用者とコミュニケーションを取る上で、大切にされていることはありますか?
■CM津﨑:
基本的なことではありますが、プランを作成する際にはご利用者としっかり話をし、できる限り多くの言葉を拾うよう意識しています。特に、お話しいただく中で「死」というテーマに触れられることがありますが、そういった言葉を見過ごさないよう心がけています。
実は、どのような最期を希望されるのか、その考え方は時間や状況によって変化することが多いのです。最初は自宅で過ごしたいとおっしゃっていた方が、その後、施設での生活を希望されるようになることもあります。お一人おひとりがその時その時で抱く思いを丁寧に記録し、今後のケアにつなげていきたいと考えています。
当初、相手の「死」を意識しながら最期まで寄り添うことに対して、正直なところ、つらく感じる場面もありました。しかし、ケアマネとしての仕事を続けるうちに、ご相談者のお話に耳を傾け、一緒に考え、その方が望む支援に最後まで力を尽くすべきだという思いが、より一層強くなりました。
自己満足に聞こえるかもしれませんが、看取りのケア(終末期の支援)に携わる中で、その支えを実現できたのではないかと感じる瞬間が時折あります。その感覚は、高校生だった頃に、祖母が急に余命を宣告されたときの経験が影響しているのかもしれません。
■あいらいふ:
今までで一番、印象に残っている出来事は何ですか?
■CM津﨑:
あるご高齢のご夫婦のことが、今でも忘れられません。100歳近いご主人が「最期は自宅で迎えたい」と強くご希望されていたのですが、介護をされていた奥さまも90歳を超えていて、まさに老老介護の大変な状況でした。それでもご夫婦はとても仲が良く、奥さまもご主人のお気持ちを尊重し、献身的に介護をされていました。
私も、このご夫妻の大切な思いを叶えたいと考え、訪問介護や訪問看護、さらに定期巡回などを活用して、奥さまの負担が少しでも和らぐような介護プランをご提案しました。
そして、ご自宅での介護が続く中にご主人は奥さまに寄り添われ、穏やかに旅立たれました。「頑張ることができて本当によかった」という奥さまのお言葉をいただいたとき、少しだけでもお力になれたのならという思いで胸が熱くなりました。
チームワークの大切さ
■あいらいふ:
利用者にとって最適なケアを実現するうえで、鍵になる要素は何でしょうか?
■CM津﨑:
ご本人やそのご家族の思いに寄り添うためには、仕事を共にする仲間であるチーム内で強い信頼関係を築くことが欠かせません。
施設でも、居宅でもケアマネの職務は一人だけで完結するものではありません。私自身も不安になることがありますが、そんなときには、訪問看護師さんや医師、ヘルパーさんなど、多くの専門職と連携し、ご利用者にとって最適なケアを提供することを心がけています。チームワークがうまくいけば、より良い支援につながりますし、利用者さんにとっても安心感につながると思います。
■あいらいふ:
良いチームを作るためのポイントはあるのでしょうか?
■CM津﨑:
経験上、一番大事なのは感謝の気持ちを忘れないことです。ケアマネとして、介護保険制度の中で調整役を務めることが多いのですが、実際に現場でご利用者の介護に携わってくださるヘルパーさんや他の関係者の姿を見ると、その役割がどれだけ重要かを実感します。そういったパートナーの皆さんに対して、「いつもありがとうございます」の気持ちを常に持つように心がけています。さらに、計画書や支援内容についてご指摘や質問が寄せられた際には、まずは相手のお話を丁寧にうかがうことを大切にしています。その後、どうすればご利用者に最適な支援が提供できるかをきちんと検討し、対話の場を持つように心がけています。
■あいらいふ:
チームワークを向上させるために工夫していることはありますか?
■CM津﨑:
情報共有のスピードを上げるために、信頼性の高いSNSを活用しています。そうすることで、皆さんの状況を迅速かつ的確に共有できます。従来の電話やメールと比べて、情報伝達のスピードが大幅に改善されていると実感しています。今後もさらに多様なツールを取り入れ、チームワークをより強化していければと考えています。
ご利用者とご家族にとっての「最適な支援」を模索する
■あいらいふ:
ご家族が多いという津﨑さんの家庭環境も、今の仕事に活きているのでは?
■CM津﨑:
それはあるかもしれません(笑)。家族が多いと、それぞれの役割や家事分担が自然と決まってきます。たすきをつなぐ駅伝のように、家族一人ひとりが自分の役割を果たすことで、スムーズな連携が生まれます。
実は私、中学校時代は駅伝に打ち込んでいたんですよ。京都市内の駅伝の強豪校で、朝も昼も夜も練習に明け暮れる日々でしたが、辛い練習を乗り越え、目標を達成したときの喜びは格別でした。
6人兄弟の長女として、駅伝チームの一員として、力を合わせて何かをやり遂げたときの充実感。それは、介護の現場で、チーム一丸となって目標を達成したときに感じる喜びと似ています。
これからも、ご利用者とご家族にとっての「最適な支援」を模索しながら、チームワークでシニアライフに寄り添っていきたいと思います。
高齢社会の未来を支えるために
■あいらいふ:
最後に、これからの目標について教えてください。
■CM津﨑:
超高齢社会に向けて、柔軟な支援策の確立が急務だと感じています。現在の介護保険サービスだけでは、高齢者それぞれのニーズに完全に応えるのは難しい状況です。例えば、外出支援や趣味活動へのサポートといった介護保険外のサービスは、高齢者の生活の質を向上させる上で非常に重要な要素だと思います。
公的制度と連携し、幅広いアプローチで一人ひとりの暮らしを支援できる体制を築くことが、これからますます求められるのではないでしょうか。また、私自身が子育てをしながら働く中で、子育て世代がケアマネとして働き続けられる多様な働き方のあり方を示すことも私の目標のひとつです。「介護業界で働きたい」といった熱意がありながらも、子育てを理由に退職を余儀なくされる方が少しでも減る社会にしていけたらと考えています。働きやすい仕組みづくりを強化することで、業界全体の活気も取り戻せるのではないかと期待しています。
その実現のため、今後もさらなる経験を積んで、支援の幅を広げながら自身も成長を続けていきたいと思います。まだまだ未熟な点もありますが、「何でもご相談ください」と胸を張って言えるような、頼られるケアマネになれるよう、日々努力を重ねていきます!
【プロフィール】
株式会社 サクセスフルエイジング
居宅介護支援事業所 まごのて北山 管理者
津﨑 朋美
京都YMCA国際福祉専門学校卒業後、京都市内にある老人保健施設に就職。10年間の現場を経験した後、CMとしてキャリアスタート。その後老人保健施設から地域包括支援センターへ転職し、現在は居宅介護支援事業所にてケアプランの作成に携わる。
===取材協力===
株式会社 サクセスフルエイジング 居宅介護支援事業所 まごのて北山
京都府京都市北区紫竹東高縄町51-4
https://www.magonote-group.com/office/kkaigo-kitayama/
取材・撮影 / 鈴木孝英
文 / 山田ふみ
豊かなシニアライフのための情報誌『あいらいふ』編集部
【誌名】『あいらいふ』vol.176(2025年3月27日発行号)
【概要】初めて老人ホームを探すご家族の、施設選びのポイントをさまざまな切り口でわかりやすく解説。著名人に介護経験を語っていただくインタビュー記事のほか、人生やシニアライフを豊かにするためのさまざまな情報や話題を取り上げて掲載。
【発行部数】4万部
【配布場所】市区役所の高齢者介護担当窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・病院・薬局など1万か所












