【ソーシャルワークの現場から】[東京]東京新宿メディカルセンター / 医療ソーシャルワーカー・ 太田 英恵 氏

医療ソーシャルワーカー・太田英恵 氏
medical social worker/Ota Hanae
ソーシャルワークは“想像”と“創造”
入院患者さんとご家族が安心して治療・療養に専念できるよう、また退院後にも安心して暮らせるよう、心理的・社会的問題を解決するための支援や調整を行う医療ソーシャルワーカー(以下、MSW)。今回は、東京・新宿区の東京新宿メディカルセンターで、がん相談の専従担当として勤務する太田さんに、お話をうかがった。
“解決力”を育てる
■あいらいふ編集部(以下、あいらいふ):
本日はお時間をいただき、ありがとうございます。まず、MSWのお仕事を志したきっかけからお聞かせください。
■医療ソーシャルワーカー・太田さん(以下、MSW太田):
高校を卒業して、大学に進学する際、自分が一体何をしたいのかと考えたときに、福祉かなと思えたことが大きかったですね。
どういった仕事があるのか調べていく中で、人の話を聞くことが好きだったり、その方の人生に触れられるような仕事をしたいという思いがあって。それなら相談に乗る仕事かな、と。カウンセラーになることも考えたのですが、やはり福祉という分野が、自分にとって一番しっくりきたんです。
社会福祉の大学を卒業して、最初に就職したのは千葉県の病院です。ちょうどそこが、在宅介護支援センター(※現在の地域包括支援センターにあたる)を立ち上げた時期で。センターに5年ほど勤めた後、併設の病院に異動。そこから何年か勤めて、東京新宿メディカルセンターに転職しました。こちらには、20年近く勤めています。
■あいらいふ:
四半世紀にわたるキャリアの中で得た、太田さんの考えるMSW像とは、どのようなものでしょうか。
■MSW太田:
MSWは、本当に幅広い仕事だと思います。今でこそ、急性期の病院では入退院支援がメインの業務になっていますが、例えば、患者さんの治療とお仕事の両立のための支援もしますし、経済的なご相談にも乗ります。
また、救急病院では特に、虐待のようなご家庭内の問題や、さまざまな困難を抱えた方も大勢いらっしゃるので、そういった方たちと“ともに考える” “ともに進む”、そういった仕事かな、と。
■あいらいふ:
患者さんのご相談に乗る際に、心がけていることはありますか?
■MSW太田:
第一に、患者さんとご家族が何を大事にされているか。ご本人の人となり、抱えている状況をとにかくよく知ることですね。どのようなことに困っていて、どのように解決しようとしているのか、教えていただきながら進めていきます。
自分自身の最終的な目標は、MSWがいなくても自分たちの力でやっていける、何か困ったことがあれば、またあそこに相談に行けばいいや、と思ってもらえること。ともに考えながら、患者さんとご家族に、そういった “解決力”をつけていただくことが、理想的なソーシャルワークだと思っています。
■あいらいふ:
さまざまにご事情の異なるご相談に乗りながら、自分の中にある“解決力”を育ててもらう。なかなか大変な取り組みではないでしょうか。
■MSW太田:
そうですね、難しい。でも、お話をして必要な情報が整理できたことで、ご自分で解決できるようになる患者さんやご家族も、とても多いんです。
もちろん、支援のための社会資源や公的制度につないだり、行き先を決めていく流れを作ることも重要ですが、お話をする、ご自身のお悩みを整理するといった、形があまり見えないものに注意を向けるのも、MSWの業務における大切な要素です。
■あいらいふ:
東京新宿メディカルセンターさまが、そういった仕事の進め方に適している点はありますか?
■MSW太田:
当院は、急性期病棟だけではなく、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、緩和ケア病棟など多岐にわたる機能を備えているので、一般的な急性期の病院よりも、比較的長期にわたって患者さんへの支援が行える面はありますね。
長い方では、急性期の治療を終えた後に、回復期リハビリテーション病棟に移られて過ごされるケースもあります。加えて、そこから定期的な外来に切り替わった方のご相談にも乗っています。
もちろん、当院だけでは解決できず、他の病院に引き継ぎをお願いすることもありますが、その場合も、患者さんが抱えている思いを次のご担当者につなげながら、最終的な解決にたどり着くまで支援することが、私たちの仕事だと思っています。
■あいらいふ:
太田さんの考える、MSWに欠かせない素養とはどのようなものでしょうか。
■MSW太田:
やはり、人間が好きかどうかが、とても大切だと思います。まず、相手を知りたいと思える感性があるか。患者さんやご家族にとどまらず、相手を思いやることができるか。病院内の多職種連携や、他の医療機関・地域の皆さんとの連携なども含めて、そういった部分が大きい。
私自身は、MSWを、“想像”と“創造”の仕事だと思っているんです。
まず、この方は今、どのような境遇にいらっしゃるのかという、患者さんを理解するための“想像”。そして、少しでも患者さんの望む生活に近づけられるよう、支援をつなぐ際に足りない部分を埋める“創造”。
難しくはあるけれど、もしかしたら、ちょっとでも工夫することで何かが変わるのではないか。そんな希望を持ち続ける姿勢が、MSWには必要だと思います。
“生き方”を決める、緩和ケアのあり方
■MSW太田:
私自身は現在、がん相談を専従で担当しています。当院には緩和ケア病棟があるので、緩和ケアに移行しつつある方のご相談がとても多い印象です。治療中の患者さんのご相談にも乗りますが、どちらかというと緩和ケアに向かう方のご相談が大半ですね。
積極的な治療が難しい、といった告知を主治医から受けた後、お話をうかがいます。また、他院で治療されていた方から、緩和ケアのことを知りたい、とご連絡をいただくこともあります。
■あいらいふ:
お身体の状況が変わってくる状況下で、不安を抱えておられる患者さんのご相談に乗るときに、気をつけなければならない点はありますか?
■MSW太田:
現在の状態をどのように受け止めていらっしゃるかによっても、まったく変わってくると思います。どのように生きてこられたか、どのような思いを持ってこられたか。そういったお話から、次の療養をどう考えていこうかという話題につながっていくことが多いですね。
■あいらいふ:
ご相談の内容によって、今後の治療方針が変わるケースはあるのでしょうか?
■MSW太田:
それは、ありますね。緩和ケアで、というお話で患者さんがお見えになったとしても、患者さんやご家族のご希望が、まだあきらめたくないというものであれば、例えばセカンドオピニオンの方法をお伝えしたり、主治医ともう一度、話し合う機会を設けることもあります。

■あいらいふ:
緩和ケアのソーシャルワークが、一般的なソーシャルワークよりも難しいと感じることはありますか?
■MSW太田:
特に難しいという区別はしていません。回復期の患者さんであっても、突然ご病気になられて麻痺が残ってしまい、治療しなければならないといった難しさもあると思います。ほかにも、例えば虐待を受けて来られた方となれば、また違った難しさがあるので。
地域が創る病院、病院が創る地域
■あいらいふ:
東京新宿メディカルセンターさまは、地域医療支援病院としての承認も受けています。地域の協力医療機関との連携も盛んだとうかがっていますが。
■MSW太田:
当院は、“地域が創る病院、病院が創る地域”というスローガンをもとに、地域とともに成長していく方針を掲げています。地域に根付いた運営という考え方は、前身の東京厚生年金病院の時代から変わっていませんね。
地元のかかりつけ医の先生と一緒に連携のための会を実施したり、ケアマネジャーさんや訪問看護師さんと事例検討を行ったり、そういったことも昔から企画して、手を携えながら進めています。
1000床規模の大学病院が立ち並ぶ新宿エリアの中では、かなり地域密着型の病院だと思います。入院や通院されている患者さんも、大半が新宿区・文京区にお住まいの方ですね。
■あいらいふライフコーディネーター・菊池美穂(以下、ILC菊池):
私の担当しているエリアでは、いまだに「東京厚生年金病院」のお名前で覚えているご相談者も大勢いらっしゃいます。
■あいらいふ:
地元の方からの信頼が厚く、長く親しまれている印象ですね。太田さんにとって、印象深い患者さんのエピソードはありますか?
■MSW太田:
最近、特に気がかりなのが、独り暮らしの患者さんが急増していることです。都市部のこの地域は、特に多いですね。
道端で倒れて運ばれて、末期のがんだと宣告された患者さんが、家族には絶対に伝えてほしくないとおっしゃって悩んだケースもありますし、認知症を患った患者さんでご家族の連絡先がわからず、最終的にお亡くなりになったあとで、近しいご家族がいらっしゃることが判明したり。
そういったことがあると、もう少し何かできなかったのか、病院だけでなく、地域として何かできることがなかったのかと思いますね。病院にいらっしゃって、そこからご自宅に戻られる方、違う場所に移られる方といった違いはあると思いますが、
その中で、ご本人が考えていたであろう将来像と、まったくつながっていかないケースがある。その点に関しては病院だけでなく、地域として、社会全体として考えていく必要があると思います。
■あいらいふ:
昭和の頃にあった、近所付き合いといった関係性も希薄になりましたからね。
■MSW太田:
そうですね。逆に、こんなところに助けてくださる方がいらしたんだと、ちょっとうれしくなった例もあります。
認知症と診断された高齢の患者さんが、毎朝ご飯を買いにご自宅から商店街のコンビニに通っていたケースで、通り道にあるお店の方が、今朝は何時に通ったと、確認してくださっていたんです。通りかからない日は何かあったかも、と連絡を入れてくださるんですね。
本当にたまたま、近くに住んでいらっしゃるというだけで、毎日。高齢者を、地域で見守る仕組みができていたんですね。その患者さんには、最終的に後見人の方が就かれたのですが、地域の方のところにもご挨拶に来ていただいて。結果として、通常よりも長くご自宅で生活を送ることができました。
■あいらいふ:
素晴らしいお話です。本来であれば、そういった地域と患者さんをつなぐ仕組みを、入院の手前の段階で、いろいろなところに作っておかないといけませんね。
■MSW太田:
実際にネットワークができれば、今よりも少しでも長く、住み慣れた場所で生活できるのかなと感じます。
歩幅を合わせて、患者さんとともに
■あいらいふ:
東京新宿メディカルセンターさまの入退院支援は、患者サポートセンターが担当されています。太田さんは現在、そちらの主任ソーシャルワーカーとしても活躍されていますが、現場のチームワークについてお聞かせください。
■MSW太田:
現在、入退院支援には、MSW5人、退院支援看護師4人、入院前支援担当看護師2人の11人体制であたっています。業務の内容がオーバーラップしますので、仕事の進め方については、連携事務を含めたセンター全体のチームワークを重視しますね。支援の方向性についてチームで話し合い、ある程度の方針を決めてから取りかかります。
■あいらいふ:
医師をはじめとする専門職や、その他のスタッフを含めた多職種連携はいかがでしょうか。
■MSW太田:
以前、当院で職員向けの満足度調査を行ったことがあるのですが、上がってくる意見の中で一番多かったものが、多職種連携が取りやすい、しっかりとした横のつながりがある、でした。
院内でがん患者サロン(患者さんやご家族が、がんのことを気軽に語り合える交流の場)を企画したときも、緩和ケア認定の看護師さん、がん専門の看護師さんと連携しながら、一緒に作っていきましたね。
■あいらいふ:
連携をしやすくするための、仕組みのようなものがあるのでしょうか?
■MSW太田:
院内の仕組みというよりは、勤めている方々のチームワークだと思います。地域密着型で、一般的な大病院ではないからこそ、専門職を含む各職員が病院の内外における連携、地域とつながる必要性をより強く感じているからではないでしょうか。多職種連携については、当院の強みとして挙げられると思っています。
■あいらいふ:
患者さんの中には、高齢者向け施設へのご入居を選ばれる方もいらっしゃいます。地域連携の一環としての老人ホーム紹介業に対しては、どのような印象をお持ちでしょうか。
■MSW太田:
最近は、ご紹介してくださる会社も非常に増えてきているのですが、まず一度依頼をして、患者さんにどのような対応をしていただけるのかを確認した上で、お付き合いを続けてほしいということを、患者サポートセンターでは共有しています。
当然、一回限りで終わってしまう紹介業者さんも出てくる中で、あいらいふさんには、長い間、患者さんに寄り添って施設をご紹介いただいていますね。お持ちの情報も幅広いし、深い。ご提供いただく図版や資料もわかりやすいです。ご自宅からだとこの辺りですと、一目でわかる地図をいただいたり。
■ILC菊池:
大変うれしいお言葉です。太田さんは患者さんのことを常に第一に考えていらっしゃって。ご相談の中で得た、ご本人とご家族にとって大事な情報を的確に拾い上げて、本当に詳しく提示してくださるんです。患者さんとご家族も、太田さんを全面的に信頼されていて、面談にうかがう際も、毎回、とてもスムーズにお話に入ることができます。
■MSW太田:
住み慣れた場所を離れるのは、ご本人にとっても不安が大きいと思います。MSWとしても、その中で少しでも、「ここに入れてよかった」と思っていただいきたい。
必要な情報さえあれば、ご本人やご家族が動けるご家庭もありますし、逆に、本当に一つずつ、手取り足取り対応しなければならない患者さんもいらっしゃいます。菊池さんには、そういった患者さんのご事情ごとに、非常に細やかに対応していただいています。
ご本人やご家族のご希望や、その方の人となりをお伝えすると、菊池さんがボールを非常にうまく拾ってくださるという印象ですね。
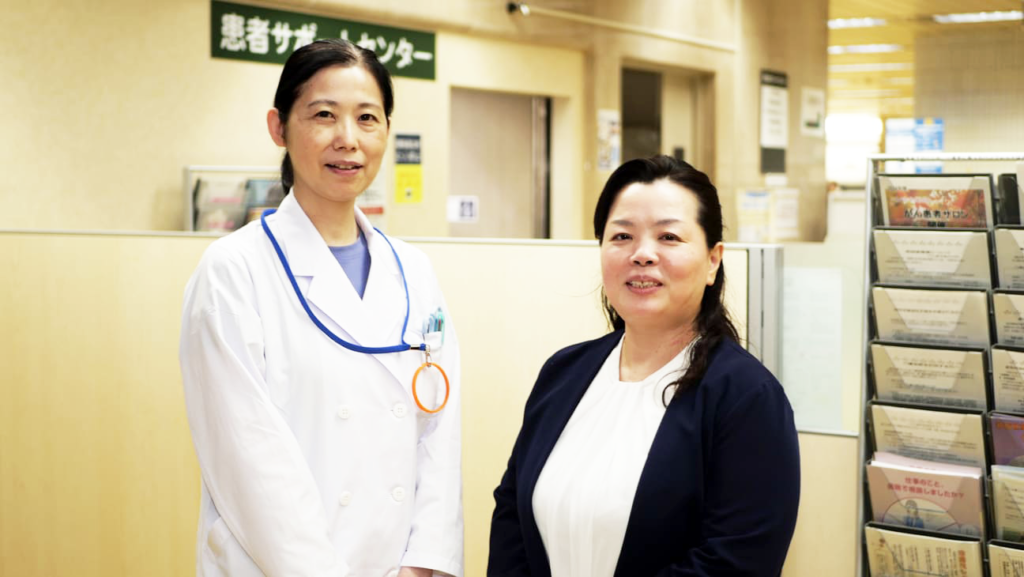
■あいらいふ:
最後に、太田さんの今後の目標についてお聞かせください。
■MSW太田:
当院は、特に受け入れる患者さんの層が幅広いので、関心を持たなければならない対象が、その時、その時で大きく異なります。求められる、必要とされる多くのことに目を向けながら、患者さんと歩幅を合わせて進んでいくのが今の目標ですね。
もちろん、後進の指導や、自分がいなくても成り立つ組織づくりをしなければならない年齢には近づいているのですが、そこはあまり気負わずにやっていこうと思っています。
■あいらいふ:
自然体で、多くの患者さんとともに歩まれるのが、太田さんの“仕事の流儀”ということですね。本日はありがとうございました。
【プロフィール】
独立行政法人地域医療機能推進機構
東京新宿メディカルセンター
患者サポートセンター主任ソーシャルワーカー
社会福祉士/精神保健福祉士 太田英恵
社会福祉の大学を卒業後、千葉県の病院が立ち上げた在宅介護支援センターに就職し、MSWとしてのキャリアをスタート。東京新宿メディカルセンターには前身の東京厚生年金病院時代から勤務し、同院での経験は20年近くに及ぶ。現在は患者サポートセンターの主任ソーシャルワーカーを務めながら、がん相談の専従担当として活躍している。
===取材協力===
独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター
東京都新宿区津久戸町5-1
https://shinjuku.jcho.go.jp/
取材・文・撮影/あいらいふ編集部
豊かなシニアライフのための情報誌『あいらいふ』編集部
【誌名】『あいらいふ』vol.174(2024年12-2025年1月号)
【概要】初めて老人ホームを探すご家族さまの施設選びのポイントをさまざまな切り口でわかりやすく解説。著名人に介護経験を語っていただくインタビュー記事のほか、人生やシニアライフを豊かにするためのさまざまな情報や話題を取り上げて掲載。
【発行部数】4万部
【配布場所】市区役所の高齢者介護担当窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・病院・薬局など1万か所












