【ソーシャルワークの現場から】[京都]ケアセンターまれびと / 介護支援専門員(ケアマネジャー)・ 加藤 圭祐 氏

介護支援専門員(ケアマネジャー)・加藤圭祐 氏
care manager/Kato Keisuke
ご本人が望む余生の代弁者でありたい
介護を必要とする方やご家族の相談に乗り、適切な介護サービスが受けられるようにサポートすることが、ケアマネジャー(以下、ケアマネ)の大切な仕事。「目の前のSOSを差し置いて、効率を上げる意味はあるのか」と悩んだ末に、自身の居宅介護支援事業所を設立した加藤さんにお話をうかがった。
介護とは無縁の若き日々
■あいらいふ編集部(以下、あいらいふ):
本日はお時間をいただき、ありがとうございます。最初に、ケアマネになるまでの経緯についてお聞かせください。事前におうかがいしたお話ですと、加藤さんはそこに至るまでのご経歴が、大変に充実していらっしゃいます(笑)。
■ケアマネジャー・加藤さん(以下、CM加藤):
出身は、現在の京都市西京区。品のあるところで生まれました(笑)。保育園のときに隣の向日市に引っ越して、そこで育ちました。
小学生のときはとにかく落ち着きのない子どもで、先生の話を聞いておらず、しょっちゅう叱られていましたね。
中学生の頃は京都大学に行こうと思っていたので(笑)、高校では代数幾何の授業を選択したのですが、これがまったくできなくて。早々にあきらめて、映画館通いとアルバイトに明け暮れていました。
卒業が近づいてくると、代数幾何の授業は週一回だったはずが、連日のように補修を受けるようになって。最後の方は、同じ問題の解法を先生が何度もささやいてくれるのを書き取って、卒業させてもらいました(笑)。
■あいらいふ:
大学時代は、民俗学に興味を持たれていたそうですね。
■CM加藤:
民俗学の授業を担当していた先生に進められて読んだ、民俗学者・宮本常一の『忘れられた日本人』という本が本当に面白くて。彼は人々の体験談を聞くことを重視して、文字で書かれた歴史からは忘れ去られた人々に焦点を当てた人なんです。
僕もいまは、ご相談者にご自身のお話をしていただくという、少しだけ似たような仕事をしているので、勝手に縁のようなものを感じています(笑)。
あとは大学で音楽に目覚めて、パンクバンドを組んでいました。ギターボーカルを担当して、髪の毛は金髪や真っ赤。成人式のときの集合写真が、一人だけ金髪でした。
挙句の果て、ちょっとプロを目指してみたり。パンクバンドでプロなんて、まあ無理な話ですけど、若気の至りで。バンドはほんまに楽しかった。卒業後も大阪でアルバイトをしながら、好きなことばかりしていました。
子どもの頃の思い出をきっかけに
■あいらいふ:
20代では青春を謳歌していた加藤さんが、ケアマネという仕事と出会ったきっかけは?
■CM加藤:
30歳で押し切られて結婚して、娘が生まれたんです。「ちゃんとせなあかん」と考えるようになって。
しばらくして、両親にも地元に帰ってくるよう説得されました。京都で腰を据えて働きたいが、何でも構わないというのは嫌。できれば人のためになるような仕事を、と考えあぐねていたときに、ずっと介護の仕事をしていた妹に話を聞いたんです。
最初に話を聞いたときは、ピンと来ませんでした、正直。ところがあとになって思い返してみると、僕は子どもの頃から、おじいちゃん、おばあちゃんの話を聞くことが好きだったと気がついたんです。
実の祖父や祖母もそうですけど、当時は、近所のおじいちゃんやおばあちゃんたちにも良くしてもらっていて。その方たちの昔話がとても好きだったんですよ。
知らないことをいろいろ教えてくれるし、人として大切なことを身につけている。理屈でなく、身体に染みついてる、というのかな。それを代々受け継いでいるのが、やっぱり日本人の良いところだな、と。
いま、振り返ってみて思うことですが、昔話が好きだったのは、その雰囲気を感じ取るのが好きだったのだと思います。
直接の介護ではないけれど、お話をうかがってご相談に乗る、対人援助という仕事があることを知って、介護業界の門を叩きました。
“効率よく”なんてできない
■あいらいふ:
当初から、ケアマネになることを目標にされていたのですね。
■CM加藤:
そうです。当時は介護現場での経験と、介護福祉士としての経験を合わせて、5年間の実務経験が必要でしたから、特別養護老人ホームやグループホームに勤めて、念願のケアマネになりました。
■あいらいふ:
ケアマネとして就職されてから、早くも2年後には独立を果たされ、居宅支援事業所を立ち上げます。
■CM加藤:
最初は、ケアマネ資格を取ったら来てくれとかねてから言われていた、元同僚の事業所に勤めました。
まずは、管理者兼サービス提供責任者として、ケアマネとヘルパーを兼務してくれと頼まれたんです。それでケアマネの仕事ができますかと聞いたら、それはもう、ちゃんとできるからと。いざ始まってみたら、ずっと現場のヘルパーさんです(笑)。
どうしてもケアマネの仕事がしたくて、直談判して所長の仕事を回してもらっていました。でも、そもそも私と向こうでは、仕事に対する考え方が違っていたんですね。所長からしてみれば、自分の事業所を経営していかなければいけないのだから、仕方のないことではあるのですが。
例えば、ご相談者のお宅を訪問するモニタリングは基本、月に一度。でも、ご相談者からは何度も呼び出しを受けることがあるんです。その都度、ご相談者のところに出向いていたら、モニタリングは月に一度を守るように、もっと効率よく動くように言われました。
それが、自分の中で違和感につながった。しわ寄せというか、事務仕事なんて後で自分たちでかぶればいい。とりあえずいま、自分が求められていることに、できるだけ応えたかった。
目の前のSOSを差し置いて求める“効率”とは、何なのか。思い悩んだ末に一念発起し、当時の同僚と二人で、13年前に独立しました。
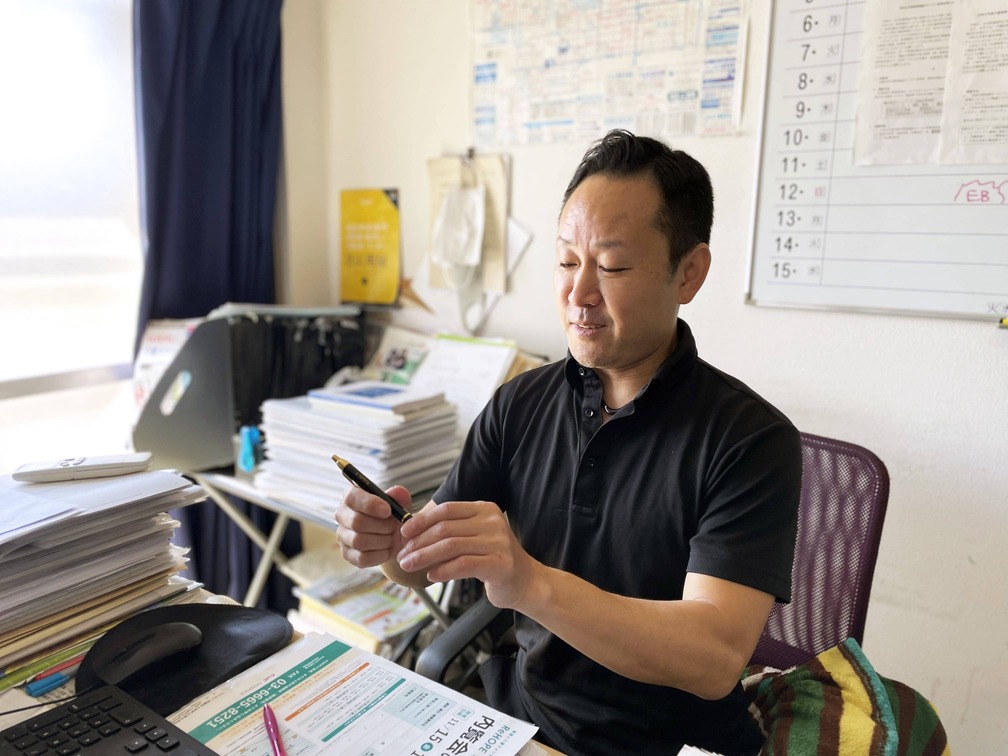
「まれびと」に込めた願い
■あいらいふ:
行動力の裏には、ご相談者に対する想いがあったのですね。
■CM加藤:
本当に勢いですね。そのときは志というか、熱い想いがあった。自分の思い描いたご相談者との関わり方ができれば、自分も嬉しいし、喜んでもらえるんだと思っていました。
今になってみると、それは続かないって、わかるんです。ただ、そのときはまだ駆け出しで、右も左もわからなかったので。
対価の発生しない細かい仕事、シャドウワークと言いますけど、ケアマネって、シャドウワークの塊みたいな仕事なんです。本来の業務とは別に、ここまではいける、これ以上はしたらあかんと自分で線を引く必要がある。線引きをしないと、本当に際限がなくなります。
でも、その頃は、全部引き受けていた。特に相手が一人暮らしの方だったりすると、昼夜を問わず駆けつけたりもしていました。当時の僕にとっては、それが本当に充実した日々でした。
■あいらいふ:
加藤さんが立ち上げられたのは、「ケアセンターまれびと」。面白い事業所名ですね。
■CM加藤:
カタカナにして、ご相談者が覚えられるのかわからない名前は嫌やなと思って(笑)。
これは、民俗学者の折口信夫が唱えた言葉です。日本には、常世というところから「まれびと」(高貴な客人)がやってきて、村に恵みをもたらしてくれるという信仰があるそうなんです。
そんなところから、この事業所とご相談者にとって、お互いが幸福をもたらす存在でありたいという願いを込めました。
この説は、折口信夫の師匠の柳田國男に酷評されたそうなんですが、僕はそんな反骨精神も含めて、彼のファンなんです。
すべてのシニアが主人公
■あいらいふ:
ご相談者との印象深いエピソードはありますか?
■CM加藤:
印象に残っているのは、独立して間もない頃のご相談者ですね。頻繁にご近所トラブルを起こす、身寄りのない独り暮らしの女性。
担当していただいている地域の民生委員の方にあいさつに行ったら、「大変ですよ、あの人は。トラブルメーカーで有名でね」と言われたんです。
確かに、最初は訪問するたびに怒られていました。でも、だんだん打ち解けていきました。自分でいうのもおこがましいですけど、その方には、長い人生の中で、そこまで関わってくれる人、親身になってくれる人がいなかったんじゃないかな。
遠慮がないせいで、付き合いにくいと遠ざけられてしまうような人。僕は、逆にそういう人が好きなんです。
僕も京都ですけど、ザ・京都というか、言葉ではすごく良いことを言って、お腹の中では…という腹芸が苦手。それよりも本気でぶつかってきてくれる人の方がよほどやりやすいというか、共感できるんです。
その方とはすごく、相通じるものがあった。間違いなく、自分がこの方の役に立てている自覚があったし、本当に喜んでくれた、心から笑ってくれたという実感がありました。
■あいらいふ:
ご相談者との間に垣根を作らない、加藤さんの分け隔てのない姿勢が、ご相談者からの信頼につながるのだと思います。
■CM加藤:
自分では、援助しているという感覚がまったくないんですよ。ご相談者からお礼の言葉をいただくことも多いのですが、とんでもない。
僕みたいな、自分の子どもくらいの年齢の人間に、心を開いていただいて、ご自身の人生をお話ししていただいたり、ご相談をしていただけるなんて、本当にありがたいです。ご相談者お一人おひとりが、人生という物語の主人公だと思っています。
望む余生の代弁者でありたい
■あいらいふ:
加藤さんの目指すケアマネ像とは、どのようなものでしょうか。
■CM加藤:
僕は、医療・介護従事者が言いがちな「べき論」は好きではない。人間は一人ひとり違い、それぞれの生き方がある。その方の意向を最大限に尊重したいと思っています。
例えば、健康で長生きするために、お医者さんから止められたお酒を我慢しながら生活している方もいます。一方で、そんなんもうええから、残りの人生、好きなことをしたいという方もいる。
もちろん、医療の見地から言えば前者が正しいのかもしれませんけど、その人の人となりや、今までの暮らしなどを、総合的に考え合わせる必要があると思います。
専門職が“正解”を押しつければ、支援を必要としている方が委縮してしまう。「助けて」という声を挙げられなくなってしまいます。
ご本人は家で生活したい。でも、看護師さんにこうと言われたら、うまいこと言えないからね、って。自分の希望を伝えても、専門職から否定されたら、もうそこで何も言えなくなってしまいます。
さらに難しいなと思うのは、ご本人とご家族の意向が食い違った時ですね。
まだまだご自宅で生活できる方なのに、「面倒見てもらっているし、施設には入りたくないけれど、子どもが言うからもう入るわ」と。本意ではない選択をしたことを悔やむご相談者を、目の当たりにしてきました。
ご本人の望む余生があるのに、いわれのないプレッシャーを感じている方の代弁者になる。それが自分の役割の一つだと思っています。
■あいらいふ:
素晴らしいお話です。数ある選択肢の中から、施設へのご入居を検討される方もいらっしゃいますが、加藤さんは、老人ホーム紹介業者にどのような印象を持たれていますか?
■CM加藤:
一般論でなく、「まごころ入居相談(※)」さんに限って言えば、めちゃめちゃ助かっています(笑)。
※株式会社MIKAWAYA21と株式会社あいらいふの共同事業
信頼している先輩にも「それはお手上げやろ」と言われたケースをご相談したら、さほど時間もかからずに「ご紹介できます」と言っていただけたことは忘れません。いまは紹介業者さんもたくさんあって、こんな小さな事業所にも何十社からお声がけいただくんですけど、まごころさんは別格です。
そういった意味でも、紹介業者さんには、ご相談者さんの願いを一緒に叶え、実現させるためのパートナーになってもらえると、心強いですね。

【プロフィール】
ケアセンターまれびと
ケアマネジャー 加藤圭祐
30代で介護の道に進み、特別養護老人ホーム、グループホームでの5年間の勤務を経て、ケアマネジャーに。38歳で独立し、居宅支援介護事業所「ケアセンターまれびと」を立ち上げる。
===取材協力===
ケアセンターまれびと
京都府京都市中京区西ノ京伯楽町14-52 マンションいそい伯楽302
取材・文・撮影/鈴木孝英
介護情報誌『あいらいふ』編集部
【誌名】『あいらいふ』vol.174(2024年12月-2025年1月号)
【概要】初めて老人ホームを探すご家族さまの施設選びのポイントをさまざまな切り口でわかりやすく解説。著名人に介護経験を語っていただくインタビュー記事のほか、人生やシニアライフを豊かにするためのさまざまな情報や話題を取り上げて掲載。
【発行部数】4万部
【配布場所】市区役所の高齢者介護担当窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・病院・薬局など1万か所












